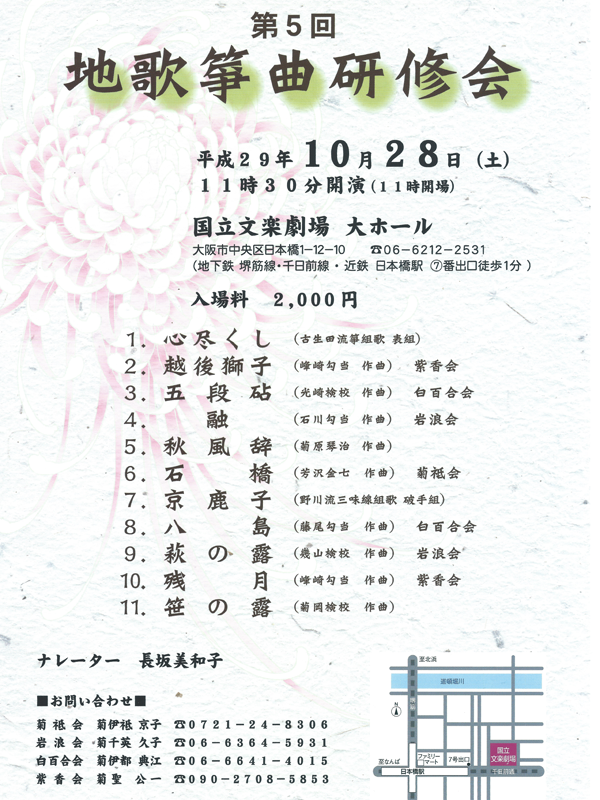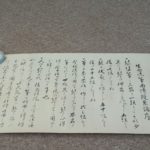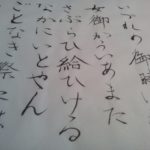ベランダに置いてあるメダカのビオトープ。ここからアクアリウムにハマり始めました。
飼うなら絶対コレ!と決めていたベタ。もう可愛くて可愛くて仕方ありません。デスク横でいつも一緒。
息子の部屋にある60センチスリムの水槽。色取りなお魚が入ってます。
リビングに置いてあるハーフムーンベタの水槽。我が家のアイドルです。
ミスト式で立ち上げ中の45センチ水槽。ほぼ流木で構成したお陰で、カビとの戦いです。注水できるようになるまで
あと1ヶ月くらいかなぁ?
レイアウト中の60センチ水槽。リスペクトしている某アクアリストさんのコンテスト作品のオマージュです。
でもやっぱり難しい・・・
可愛い可愛いベタの為に一昨日立ち上げた30センチキューブ水槽。デスクの1/3を占拠されました。
水槽が安定したらお引越しです。
とドンドン水槽が増えていきます。水槽やベランダのお花のお世話で毎日午前中潰れてしまってますが
楽しいから良し!